
PT,OT,STは勤続年数が短い職業です。
そのため、転職や退職を考える人は多いですよね。
リハ職が退職するにあたって、仕事上の引継ぎをするのはよく目にすると思います。
引継ぎ以外にも、退職前、退職後、さらにはママ作業療法士だったら、絶対に確認しておくべきことがあるのをご存じでしょうか?
この記事では、リハ職が退職前後にするべきこと、子どもがいる場合は特に注意が必要なことをまとめました。
参考にして、今年こそ退職しようという人は、退職前後にやることを再確認しておいてください!
退職前にやること
退職前にやること
- 就業規則を確認し、退職日を決める
- 患者治療の引継ぎや後輩指導の引継ぎ
- 転職活動
- 退職願の提出
- 保育園の利用要件の確認
就業規則を確認し、退職日を決める
就業規則には退職を告げて、どの程度の期間で退職できるのかということが明記されている場合がほとんどです。
そのため、最低でもその期間より前に退職を伝えておくことで、スムーズに退職できます。
人手が少ないなどの理由で引き留められることもありますが、この要件を満たしておけば、退職できないということはないので、就業規則を確認しておきましょう。
また法律的には民法627条で、期間の定めのない労働契約の場合、退職を申し出て2週間が経過すれば企業の承諾がなくても退職できるとされています。

じゃあ2週間前に言えばいいよね…と言うのはちょっと待った!
一般的には1~2か月前までに退職を告げた方が良いとされているので、特別な理由がなければ退職の相談は1~2か月前には行っておきましょう。
患者治療の引継ぎや後輩指導の引継ぎ
セラピスト間での引継ぎ作業も大切です。
患者の目標や治療方針が大きく変わってしまうと、引き継いだセラピストへの不信感や病院への不信感を抱く原因にもなりかねません。
患者治療を最優先で行うために、しっかりと引継ぎを行いましょう。
また、代診を頼んでいたセラピストに引き継げるならば、患者さん、セラピスト共に負担感は少ないと感じます。
患者さん自身にも退職を伝えることが必要ですよね。
いつ患者さんに伝える場合には自己判断ではなく、上司にどの程度の期間で退職を伝えても良いのかということを相談しておくことでトラブルを防ぐことができます。
リハビリ職は後輩指導もマンツーマンの態勢を取ることが多いので、指導方針に従ってどの程度の指導まで行っているのか、今後の課題などを後任に伝えましょう。
転職活動

転職活動は退職後でも、退職前でも構いませんが、注意が必要なのは子どもが保育園に通っている場合です。
私自身は、一度目の転職の時には、子どもがおらず、金銭的にも問題なく、少し休みたい気持ちが強かったので約半年ほど働かずに暮らしました。
失業保険もあるので、自己都合でも3か月後には失業保険がおり、生活費にあてることもできました。
ただ、子どもを保育園に預けての転職の場合は、通っている保育園に通い続けるための猶予期間がありました。
そのため、転職活動をしてから退職を相談しました。
退職願の提出
退職願を書いたことがない人にとっては、退職願ってどうやって書くの?と感じる人もいるかもしれません。
決まった書式がある職場も多いのですが、まずは退職願を自分で提出してと言われる場合もあります。
その際にはネット上調べれば、用紙の種類や封筒の色、縦書き、書き方の形式などの退職願の書き方はよく出てきます。
基本的に退職理由には、一身上の都合と書くのが一般的ですね。

わたしは形式の決まっていない退職届を提出してから、アンケートのような退職届けを再度提出するように言われたこともあります。
具体的に退職理由を書いてと記載があったので、率直な退職理由をかいたこともあります。
会社によって違うみたいなので、退職を上司に相談する時に書式を聞いてみましょう。
子どもがいる作業療法士なら絶対確認しておきたいこと【保育園の利用要件の確認】

現在保育園を利用している場合は、保育園の利用要件を必ず確認しておきましょう。
手続きを間違うと、最悪、退所扱いとなってしまうので、注意が必要ですよ!
重要ポイント
保育継続を希望する場合は、その要件や期間をしっかり確認すること。
次の職場へいつ転職するのかを決めるには、ママやパパの場合は保育園に通い続けられるのかどうかも必ず確認が必要です。
まずは、いつまでに仕事を決めれば保育園に通い続けられるのか確認してから転職日や、退職日を決めるべきです。

保育園の利用要件は両親の要件なので、もちろん父親にも同様のことが求められますよ。
休職期間に退所しなければいけないという地域もあるようなので、要確認ですよね…。
退職後にすること
健康保険の手続き
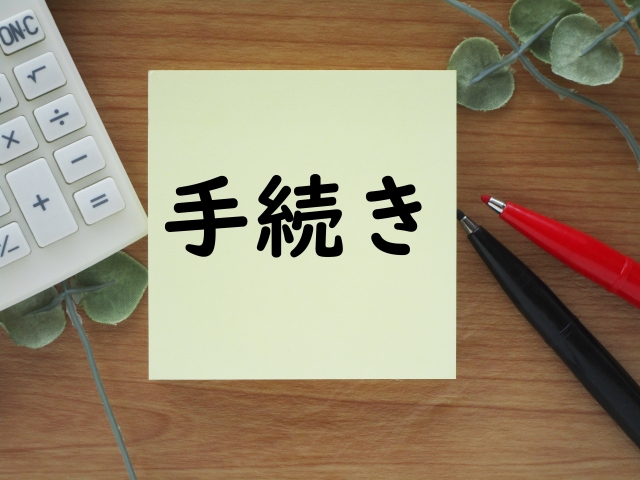
健康保険には選択肢があります。
健康保険の選択肢
- 次の職場に健康保険をうつす
- 任意継続する
- 家族の健康保険に扶養される
- 国民健康保険に入る
すぐに次の職場への転職が決まっており、在職期間があかない場合は、健康保険をすぐにうつすため、問題ありません。
しかし、いったん退職してから、働きだす場合は任意継続するのか、家族の件個保険に入るのか、国民健康保険に入るのかを選ばなければいけません。

私は退職時に職場から健康保険の任意継続についての説明もうけました。
説明が特にない場合で任意継続を希望の場合は、退職時に聞くようにしましょう。
健康保険を任意継続する場合
任意継続とは、2年間は自分の意思で健康保険を継続するという制度です。
継続する方が保険料が安いのか、国民健康保険に切り替える方が安いのかは人に寄ります。
市町村によって保険料の算定方法が異なるためです。
住んでいる市町村の窓口で相談すると、計算して教えてくれました。
国民健康保険に入る場合
国民健康保険に入る場合も確実に、市役所の窓口で手続きをしておきましょう。
国民健康保険に入る場合は、自分で年金を払う必要があります。
口座からの引き落としでの支払いにするのか、請求書に対して支払うのかも選ぶことができますよ。
家族の健康保険で不要に入る場合
家族が会社員であれば、しばらくは家族の扶養に入るという選択肢もでてきます。
その場合は、家族の会社にて手続きが必要となるので、家族と話し合って手続きをすすめましょう。

家族が会社員でなく、自営業の場合は、不要に入れないため国民年金に入るか、任意継続をするかの2択になります。
年金の手続き

年金も同様にすぐに次の職場へ転職しない場合には、自分で役所へ行き手続きが必要です。
1日でもブランクがある場合には、国民年金への切り替えが必要となります。
国民年金に一度加入する場合は、必要物品を確認して、居住地の市町村の窓口へ行くと手続きができます。
離職票が必要となるので、退職時にどの程度で離職票がもらえるのか確認しておきましょう。
また、職場が厚生年金基金などに加入している場合は、年金としてうけとるのか、一時金として受け取るのか選ぶこともありますので、考えておきましょう。

実は私は最初の転職時に、年金未払い期間が生じていました…。
自分でも気づいていなかったのですが、後から送られてきた督促状に応じて払えば、未払いをなくすこともできるので、安心してください。
所得税や住民税の手続き
退職後は所得税、住民税についての手続きも注意が必要です。
すぐに次の職場で働く場合には、手続きは不要ですが、無職の期間がある場合には注意して下さい。
注意と言っても、住民税は退職後に会社からの天引きがなくなり、特に手続きをしていなくても支払い用紙が個人あてに送られてきます。

支払いが発生することを知らなかったら、急に支払い用紙がきたらびっくりしますよね。
知っているだけで、詐欺ではなく普通に住民税の支払いだと認識できますね。
また、住民税の支払いが生じるということを知っていると、生活費も具体的に考えれるようになります。
年末調整が必要な場合もある
年末調整をすることで、所得税が返ってくる場合があるため、年末調整をした方が良いです。
年末調整が必要なのはどんな時?
年の途中で退職し、年内に就職しなかった時
所得税は今年の所得を予測した金額を引かれています。
そのため、住民税とは違い、実際に支払う金額と本当に支払うべき金額の差が生まれてしまいます。
その差を返してくれるのが年末調整です。
そのため、会社内で年末調整ができない場合は、自分で年末調整をすることで、所得税が返ってくる見込みがあるのです。

退職前にもらった源泉徴収票はなくさずに持っていてくださいね!
控除をしっかり受けるためのものなので、年末調整が必要な場合は頑張ってやりましょう。
まとめ
今回は作業療法士が退職前後にすることを確認しました。
特に子どもがいる場合の保育園の要件確認は忘れずに行ってくださいね!
退職後の手続きも知っているのと、知らないのではスムーズさが違うので、手続きに必要な書類の保管や離職票の要求など忘れずに行いたいことをまとめました。
退職をした後にすることがあるというのは、私も退職してから知ったことなので、かなりの手続きがあるんだなと感じました。
難しいように感じたかもしれませんが、人事課の人も慣れていますし、市役所に行けば大概のことは教えてくれるので、要件書類を持って教えてもらいに行きましょう!

みなさんは焦らずにできるように万全の状態で転職に向けて動いてくださいね!
転職が気になるママにはこちらの記事もおすすめ。