
作業療法士が転職する時にチェックしておいた方が良い項目と言うのは、いくつもあります。
その中でも、ママ作業療法士がチェックしておくべき、項目を挙げました。

私自身も子どもを産んでからの転職経験があり、こういうことに気をつけて転職しないといけないのか…というのが実は後からわかったんです。
そのため、これから転職する人には、ママならこういった項目もチェックしてね!と強くおすすめする項目を列挙しています。
子どもの為でもありますが、自分のための転職でもあるので、しっかり将来を見据えて、自分の価値観に合うかどうかを確認してみて下さい。
ママ作業療法士が転職する際に知りたいこと
作業療法士としては、もちろん転職先の条件面であったり、経験年数のバランスなどもみると思います。
ママには追加でみてほしい項目はこちらです。
チェックしておいてほしい項目
- 子育て世帯の職員はいるのか
- 職員の男女比
- 上司の子育てへの理解
- 離職率
- 給与や昇給率が自分の価値観と合うか
- 残業代の有無
- 勉強会の頻度や出席に対する考え方
- 自宅から保育園職場の距離感
- パート等の雇用形態の柔軟性
意外に聞かずに終わってしまうのが、昇給率です。
今は給与よりも、休みやすさと割り切れるなら良いですが、外的な報酬はそれがモチベーションとなることもあります。
子育て世帯の職員はいるのか

子育て中の職員が多くいた方が、休む人が多くなるから困るのでは?と思う人もいるかもしれません。
しかし、子育て世帯が多くそこで働いているということは、急な休みの対応にも慣れており、比較的働きやすいと判断することができます。
特に、上司もその世代だった場合は、寄り添った対応をしてくれることも多いですよ。
職員の男女比

男女比をみることも、ママが働くうえでは参考になります。
もし、男性ばかりの職場環境だった場合、女性が働きにくい現状があるのか?子どもの急な休みなどには理解を示してくれるだろうか?などの疑問が浮かびます。
そもそも、作業療法の比率的に6割は女性です。
全体の比率が6割で、職場の比率が男性の方が多いとなると女性が働きにくさを感じている可能性もあります。
理学療法士の男女比は6割が男性です。
そのためPT,OTと合わせて考えるのではなく、PT、OT別でみる必要がありますよ。
上司の子育てへの理解

先ほどの「子育て世帯の職員はいるのか」の項目でも上司が子育て世帯だった場合、対応してくれやすいということは書きました。
しかし、実際には、上司への子育てへの理解というのは人それぞれです。
男性であれば、そもそも子育てにそれほど参加していない人もいます。
また、女性であっても「私たちの時代は仕事を優先したのに…」など固定概念が抜けきれずに、子育てとの両立への理解が薄い人もいます。
一方で、子育て中の職員に配慮しすぎて、他の職員への対応が不十分である場合もあります。
そういったバランス感覚を持った上司であるかどうかが、キーポイントになります。

初対面でそこまで見抜ける?と思いますよね。
正直、入ってからしかわからないこともあるんです。
そのため、見学時には「子育てをしながら働く人の割合」は大切です。
離職率
離職率とは一定期間に何人の人が辞めたのかということです。
離職率は医療業界では比較的高いことが多いです。
しかし、医療業界であっても高すぎる離職率は、何かしらの問題が隠れているけーすもあります。
休日日数や、人間関係、セクハラやパワハラ、フォローの態勢などです。

離職率なんて聞いてもいいのかな?と思うかもしれませんが、何度も転職するような羽目にならないよう聞いておくに越したことはありません。
ただ、聞き方や流れは考えましょう。
後半にサラッと聞くのが良いですよ。
離職率の概要
- 医療従事者の離職率 約15%
- 理学療法士の離職率 約19%
- 一般企業の離職率 約13~15%
厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」
厚生労働省の令和3年度の資料によると、一派企業の離職率は13~15%、理学療法士は19%と一般的にも高く、他の医療従事者と比べても高いとさわれています。

ただ、医療施設と、介護施設では介護施設での離職率は19%よりもっと高く30%代です。
訪問リハビリテーションにおいては37.4%と非常に高いですね。
一方、作業療法士の離職率については公的機関が行った統計データはありませんでした。
そのため、勤続年数を表している「令和4年賃金基本統計調査」で勤続年数を確認します。
他の職種では、平均勤続年数が10年を超えている物も多いですが、作業療法士を含めたリハビリ職全体としては平均7.3年となっています。

基本的に、リハビリ職は転職ありきで働いている人も多く、勤続年数は短めですね。
そのため、離職率を確認してみて、その業界の平均値とそれほど変わりなければ、問題ないと判断することができますね。
また、離職率が、それよりも低ければある程度人が定着しており働きやすい職場環境にあると判断できる可能性もあります。
*参照:厚生労働省『令和4年賃金構造基本統計調査 職種(小分類)
給与や昇給率が自分の価値観と合うか
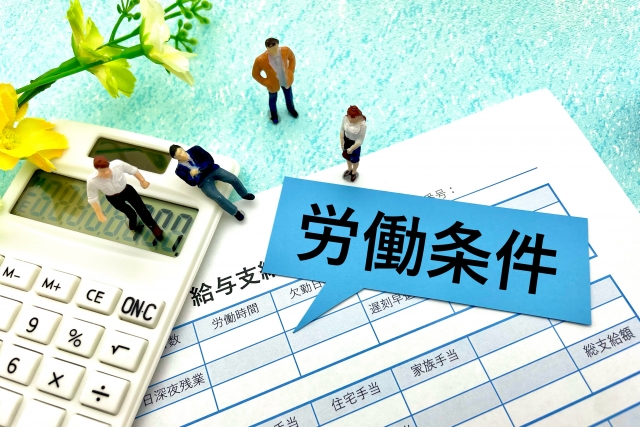
給与が少なくても、余裕を持って働けるのであれば、それでもいいというママ作業療法士は少なくありません。
そのため、大事なのは自分の価値観に合っているのかどうかという点です。
今は良くても業界内以上に、昇給率が明らかに低い職場で長年働くことができるのか?という点も考えてみましょう。
子育てはいつか落ち着く時がきます。
そして、経験を重ねるごとに、後輩指導や実習生の指導、委員会など患者業務以外のことも任される立場になってきます。
そんな時にも、その給与で踏ん張ることができるのかというのは、一つの要素ですよね。
残業代の有無

残業自体の有無も大事です。
そして、残業代はでるのか?どのような時にでるのかと言ったことはしっかり確認しておく方が良いです。
わたしは新卒で入った病院は、定時にタイムカードを押して、仕事を続けなさいと指導するような病院でした。
そのため、もちろんサービス残業。
新卒だからそんなものなのかな?と思っていましたが、転職してみ様々な職場があるのだとやっとわかりました。
勉強会の頻度や出席に対する考え方

ママになると、保育園のお迎えがあります。
そのため、勉強会への参加も制限される場合があるんです。
家族間で調整して、参加できるように設定できれば良いですが、必ずしも夫が迎えにいけるとも限りませんよね。
勉強会の頻度が高ければ高いほど、参加することができなくなってしまいます。
そして、参加できなくても何もなければ良いですが、人間関係にひずみができたり、強制的な意味合いでの勉強会の場合、職場での立場が危ぶまれます。

勉強会の強制感は、リハ職の特殊なところだとは思います。
そのため、どの程度の頻度で開催されるのか、開催する側となる場合もあるのか、参加率はなど確認しておきましょう。
自宅から保育園職場の距離感

自宅から保育園の距離感は圧倒的に近い方が良いです。
子どもを連れての移動は、一人で移動するよりも何倍も疲れるからです。
また、移動時間が短いほど、自宅で過ごせる時間も長くなりますよね。
理想は、自宅、保育園、職場が延長線上にあり距離が近いことです。

わたしは保育園が通勤の反対方向にありました。
そのため、保育園まで車で送迎し、保育園とは逆方向に車通勤で行っていたのですが、そうなると結構遠い。
通勤が遠い時期には、通勤がかなり苦痛で、7時過ぎには子どもを預ける必要性がありました。
時短勤務の取り方
時短勤務と一概に言ってもパターンがあることをご存じですか?
第一子を産んだ職場では、出勤時間、退勤時間を自由に30分、一時間、一時間半、2時間の短縮のなかから、自分で選択できるという職場でした。
第二子が生まれる頃は転職しており、違う職場で働いていましたが、その職場は退勤時間が1時間早くなる以外の選択肢がありませんでした。

これから時短勤務を取る可能性がある人は、時短勤務の有無だけでなく、時短勤務の取り方についても確認しておくとよいでしょう。
パート等の雇用形態の柔軟性
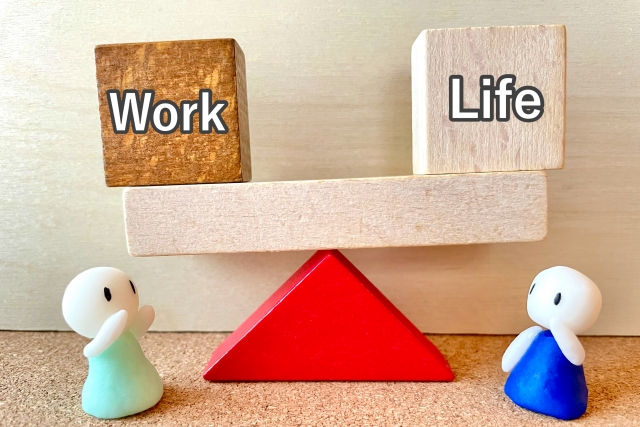
場所によっては、パート・正社員雇用を、その時期によって調整できるような職場もあります。
どういうことかというと、仕事を抑えたい時期(小1の壁など)の時にはパート勤務として働き、生活が安定してきたら正社員雇用として働くことができるというパターンです。
このメリットは、慣れた職場から転職しなくてもライフワークバランスが取りやすいことです。
すべての職場ができることではないので、入職前にパート雇用の実績を確認するのもありかもしれません。
まとめ【ママには転職時には必ずチェックしてほしい項目】
今回はママ作業療法が転職時に確認してほしいことをまとめました。
遠慮しすぎて、聞けない…など思わずにこれから子育てをするうえで非常に重要なことなので、確認しておきましょう。
項目を自分で聞くのが億劫、聞き方がわからない…と悩む場合には転職エージェントを通して聞くこともできます。
チェックしておいてほしい項目
- 子育て世帯の職員はいるのか
- 職員の男女比
- 上司の子育てへの理解
- 離職率
- 給与や昇給率が自分の価値観と合うか
- 残業代の有無
- 勉強会の頻度や出席に対する考え方
- 自宅から保育園職場の距離感
- パート等の雇用形態の柔軟性
子連れで何度も転職するにはパワーがいります。
そのため、できるだけ良い職場に巡り合うために、自分でできることはしていきたいですよね。
ママ作業療法士の悩み記事はこちら。