
人間の悩みの9割は人間関係の悩みであるとアドラーが言うほど、人間関係ってストレスになりやすいですよね。
リハビリ業界でも独特の人間関係があり、悩んでいるという人も多くいます。
作業療法士も、理学療法士も言語聴覚士も様々な人と協力しながら働く職業です。
他の職種であっても、全てが一人で完結するという職業はあまりないですが、リハビリテーション職は特に人間関係に比重を置いていると言っても良い職業ですよね。

職場は滞在時間が長いので、人間関係のストレスがあると仕事自体が嫌になってしまうこともありますよね。
先輩や上司意外にも、多職種、クライアントの関係性に悩む人を多くみてきました。
一般的に人間関係が辛いと感じる理由
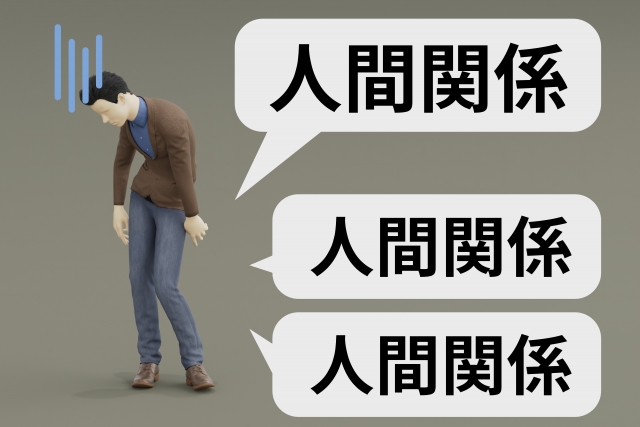
まずは一般的に人間関係に悩む時の具体例をみていきます。
一般的な具体例
- 上司や同僚、後輩から嫌われたくないと思ってしまう
- 明らかに嫌いな人がいる
- セクハラやパワハラを受けている
- 無視やいじめを受けている
- 派閥があり、それに巻き込まれている

作業療法士や理学療法士でも同様のことってありますよね。
次に、特にリハビリ業界の悩みとしての誰と?何に悩むの?というのを具体的に示します。
PT,OT,STの人間関係での悩み
リハビリ業界の人間関係においても、誰とどんな悩みがあるか挙げていきます。
多職種との悩み

DrやNs、MSWなど様々な人と退院や自宅での生活を支援するのがリハビリ職の大きな仕事です。
そのため、多職種ともよく話し合って、信頼しあって治療を進めていきたいですよね。
しかし、病院によっては、職種によって権力が強く、アイデアを提案しても受け入れられなかったり、考え方が理解しあえないと協力できなくなくなってしまいます。

多職種は患者さんに対しても違う目線で見ているからこそ、重要なチーム医療の一員です。
しかし、時には治療方針の違いでぶつかってしまうということや、業務負担によりできないと言われることもありますよね。
上司や部下との関係
上司に悩むという人も多いかもしれません。
頑張っているけれど評価してもらえていないと感じる、怖すぎて接する時に緊張してしまい何も話せない…など、上司によっては話しにくい、相談しにくいと感じる人もいるかもしれません。
逆に、上司は部下とのジェネレーションギャップで話しにくくて…気を使いすぎて…と嘆いている人も良くいますよ。
同職種同士の悩み
作業療法士どうし、理学療法士どうしなら分かり合えるかと言われれば、そんなこともありません。
治療手技などの考え方の対立によっては、多職種より険悪ということもあります。
年代が違うと、リハビリの知識や評価方法までもが違うこともあるんです。
そんな時にお互いが歩み寄り、相手のことを理解しようとしない場合は、考えの違いから残念ながら分かり合えません。

患者さんんを少しでもよくしたいって思うからこその対立の場合は、やるせないですよね。
お互いの意見を冷静に判断し、やってみたリハ結果で判断するのが良いかなと思います。
人の意見にも耳を傾ける余裕が欲しいですね。
クライアントとの悩み

患者さんとの関係で悩む場面ってセラピストなら一度はありますよね。
性格の不一致もありますが、認知症状によるものなのかの判断もつきにくい場合もあります。
また、作業療法士は理学療法士と何が違うのかよくわからないという患者さんも多いです。
そのため「作業療法士の説明」を最初にしておくというのも手ですよ。
また、男性患者さんからのセクハラに悩むセラピストも多くいるので、そんな時は患者さんだから…と我慢せずにしっかり信頼できる人に対応策がないか相談してくださいね。

私も患者さんに手にキスされてめちゃくちゃキレそうになりましたね。
家族との悩み

セラピストどうしで結婚した場合、比較的勤務や残業にも理解があることが多いです。

ただ、まれに職場環境の違いから、なぜそれほど残業する必要があるのか?とセラピストどうしでも見解の違いはでますが…。
また、全く違う職種の方と結婚した場合、リハビリテーション業界の常識が通じない場面もあります。
勉強会や、残業を理解してくれなかったり、シフト制で働くことに難色を示したりすることがあるので、家族間でも話し合っておく必要があります。

特に子どもが生まれたら、男性でも女性でも今までのような働き方ができなくなる可能性があることを理解する方が良いでしょう。
リハビリテーション職の人間関係の悩みあるある
めちゃくちゃ率直に、リハビリテーション業界での悩みや、こういった人間関係ってあるよね~というのをかき出していきます。
人間関係あるある
- 先輩の地位がやたら高い
- Nsの地位はめちゃくちゃ高い
- 派閥があるが、どちらのことも理解できない
- 徒手療法の練習と言う名のセクハラがある
先輩の地位がやたら高い
勝手な意見かもしれないですが、体育会系が多いPTで多い現象です。
PTは体育会系の人の割合が多く、縦社会となりがちです。
逆にOTやSTは少人数で仲の良いことも多いです。
ですが、人によってはやはり教えてもらう立場と教える立場にとらわれてしまって、「こんなこともわからないのか?」と威圧的な先輩もいます。
先輩は、仕事量も多く抱えていたり、家庭を持っている人も多いため時間に追われている場合もあります。
そうなると、要点をまとめて質問を受けないと、時間がないと焦ってしまい、対応が雑になってしまうこともあります。

普段から話す回数を取って、コミュニケーションしやすい状態を作っておくことが大切です。
先輩が怖すぎて無理…という場合は、「患者さんの為、これは仕事だから」と勇気を振り絞ろう(笑)
でも、本当に怖すぎて相談もできないようなら、仕事にならないので、他の相談できる人に相談してみる方が良いでしょう。
Nsの地位はめちゃくちゃ高い

看護師さんは正直、威圧的な人と、威圧的でない人に二極化しています。
ただ、威圧的な人の中にも、患者さんのことを思って言ってくれている人がいます。
このパターンの人には、感謝して、話し合いながら治療を進めていきましょう。
そして、お互いに専門職としてディスカッションできるような関係性を気づいていくのがベストです。
一方で、ストレスの多い看護師の仕事ですから、自らが病んでいるような看護師さんもたまにいるのも事実です。
この場合は、触らぬ神に祟りなしと思い、そっとしておきましょう。
どうしても今日のリーダーや、担当看護師で話さないといけない…などあれば何を話すのかを要点をまとめた上で話しかけましょう。

そして、その人のあつかいが上手な先輩に扱い方を教わりましょう。
ただし、先輩とあなたのパーソナルな情報が異なるため、全く同じ手法でうまくいくということではないと理解しておきましょう。
派閥があるが、どちらのことも理解できない

リハビリテーションの世界では手技によって、考え方が違ったり、管理者の人間関係によって考え方が違ったりすることも、正直あります。
そんな時には、派閥を気にすることは全くないと個人的には思います。
派閥として考えるというよりは、その課題に対して一つ一つ自分なりの答えを持っておくことが大切ではないかと感じるからです。
そのため、派閥に対して無理に「どっち派」などと入る必要はまったくありません。
それにより孤立するようならそこまでの職場だと割り切りましょう。
徒手療法の練習と言う名のセクハラがある

これは徒手療法の多いセラピストあるあるなのかと思います。
徒手療法でお互いの体を使って、施術を体験し、勉強するという場面はあります。
しかも、結局セクハラなのかどうか?と言われればわからないと悩んでいる人もいるかもしれません。
相手がセクハラとしてやっていなかったとしても、立場の強い人からの身体的接触を嫌だと思うなら、それは伝えて良いことだと思います。
ただ、徒手療法をしている男性からすると、真剣に教えていたのに…って思う場合もあると思うのが現実ではあります。

実際ボ〇ースなどでは立位時に大殿筋をグッとつかんで刺激をいれながら行うこともありますよね。
患者さんに対してもいつも触っているので、そのハードルが非常に低いという人もいますよ。
大胸筋を女性のセラピストも患者さんに許可を得て触ることがありますからね…。
人間関係的には、まずは信頼できる人に相談して、さりげなく回避してもらう方が無難でしょう。
職場の人間関係を解決するためには
そんなリハビリ独特の悩みもありますが、解決するための方法を具体的にみていきましょう。
人間関係に困ったら
- 他責思考になりすぎていないか考える
- 物理的に距離が取れるなら取る
- 雑談などのコミュニケーションを意識して取る
- 信頼できる人をみつける
- 報告、連絡、相談はこまめにする
- 異動や転職をする
他責思考になりすぎていないか考える
自責思考と他責思考という言葉があります。
他責思考とは、物事の原因が、他の人や、環境にあると考える考え方です。
一方、自責思考とは物事の原因や責任が自分にあるという考え方です。
いつも環境や、他人のせいにする癖がある場合、その思考から抜け出せずにいる場合があります。
そして、そういった場合は環境を変えたとしても、同じような悩みに当たる可能性があるということを知る方が良いと感じます。
自責思考の考えがある場合は、失敗した時に「自分がどうすればよかったのか?」ということを念頭に考えられます。

自制思考が強すぎても、心の負担が大きいため、ストレスにつながりやすいです。
そのため、自責思考であっても、自分を責めずぎるのは違うと割り切って考えられると、仕事上円滑に進みます。
とはいえ、自責思考ができる人は、周りからの信頼感も強くなるため、時によっては自責思考の考え方を取り入れると良いでしょう。
物理的に距離が取れるなら取る
辛いと感じるようなら、ストレスのかかる人間関係から離れるというのが鉄則です。
物理的な距離と心理的な距離はほぼ相関関係にあるので、物理的に離れることで、心理的にも距離をおくことができます。

ただ、仕事上関わっている人って自分が人事権でもない限りは、簡単に離れられないんですよね。
特にリハ職はそれぞれの職種での結びつきが強い傾向にあります。
コミュニケーションを工夫する
自責思考で考えた時の手段として、コミュニケーションを工夫してみるのもおすすめです。
共感を示しつつ、どのように相手に自分の意見を伝えるのか、このバランスが崩れてしまうと人間関係がストレスになりますよね。
例えばこんな工夫が考えられます。
例えば…
- アクティブリスニング
- アサーション
- 積極的強化
学生の時にならった、心理学の技法や、知識が職場でのコミュニケーションでも役立ちますよ。
アクティブリスニング(積極的傾聴)
しっかりアイコンタクトをとりつつ、質問や相槌を打ちながら聞きます。
相手の話をより、「聞いていますよ」とメッセージを送りながら聞きましょう。
そして遮らずに話を最後まで聞くことで、相手は尊重されていると感じます。

これはクライアントに対しても良く行っているのではないでしょうか?
これを職場の人間環境にも活かして行くことが大切ですね。
アサーション
アサーションは周囲に配慮しつつ、自分の意見を率直に伝えるためのコミュニケーション技法です。
具体的にはYOUではなく、Iメッセージを使ったり、適切な環境でのコミュニケーションを取るようにしたりすることです。
積極的強化
望ましい行動をしてもらった時に、その行動を強化するようなコミュニケーションです。
これは子育てなどでよく使われるので、子どもを育てている人にとっても大切ですね。

少しの工夫で、人間関係が円滑にいくと相乗効果でどんどん良い方向にすすむことがありますからね。
人間関係がしんどいと思う人は、工夫してみて、相手をよく観察してみましょう。
雑談などのコミュニケーションを意識して取る

心理学の世界では、ザイオンス効果(単純接触効果)とよばれるものがあります。
ザイオンス効果とは、接触回数を多くすればするほど、その人に好感を抱くようになるという心理です。

自分に置き換えても、よく話す人には気軽に自分も話しかけられるし、親しみを抱きやすいのかなと感じます。
そのため、上司や先輩の立場であっても、部下であっても基本的なコミュニケーションの量を増やすという手段は、職場での人間関係を円滑にするための一つです。
挨拶や、雑談も含めて仕事の信頼関係をつくきっかけであると思って、接してみると良いです。
また、小さなことだと思っても感謝を示す行動は誰しも嬉しい物ですよね。
報告、連絡、相談はこまめにする
報告、連絡、相談をするではなく「こまめに」という点が重要だと思います。
多くの人間関係のトラブルは、コミュニケーション不足から起こるものです。
特に、リハビリテーション職をしていて、自分だけがクライアントに関わっていると思うような振る舞いをしていると、クライアントの不利益にもつながりかねません。
そのため、チーム全体でみている意識を持ち、先輩に相談もしながらすすめることが必要になってきます。
取り返しのつかない段階で相談をされても困ります。
そのため、頻回なホウレンソウは必要であると言えます。
信頼できる人をみつける

人と人との関係は相性があり、その相性が実際に悪い場合もあります。
職場は良い意味でも、悪い意味でも集団生活です。
そのため、その集団の中には一人くらい自分が信頼できるような人がいるはずです。
その人をみつけて、話し相手や相談相手として、時には人に頼ることも必要です。
多職種連携が必要な職種だからこそ、信頼できる相手とディスカッションしながら、自分を客観的にみる機会も必要だと感じます。
異動や転職をする
色々やったけど、やっぱり無理だ…という時には、その職場から離れても良いでしょう。
異動や転職で、自分に合う場所を探すのも一手です。
転職は特に、人間関係のリセットには有効手段と言えます。
特定の苦手な人がいなくなる、集団圧力があるような職場から回避できるなど多くのメリットがあるでしょう。
転職率の高い職種だからこそ、サクッと転職するのも、自分の心を守る手段として持っているだけで、気が楽ですよ。

私自身も転職経験がありますし、転職する人を多くみてきました。
なんだかんだの理由はありますが、人間関係が良ければ継続して働こうかなと思う人が多いように思います。
まとめ
今回はリハビリテーション職の職場での人間関係に悩む人への解決策をお届けしました。
独特の文化と、人間関係を持つ職場なので、ストレスがかかることがあるかもしれません。
しかし、医療職を志す人の多くは優しい人も多いので、怖がりすぎずに、コミュニケーション方法を学んでいくことで人間関係のストレスが減っていきますよ。
色々やってみているけど、人間関係を一度リセットしてから、気持ちを立て直したいと感じる場合には転職もおすすめです。
人生は有限なので、ストレスのかかることに対してどう向き合うのかは本人の自由だと感じます。